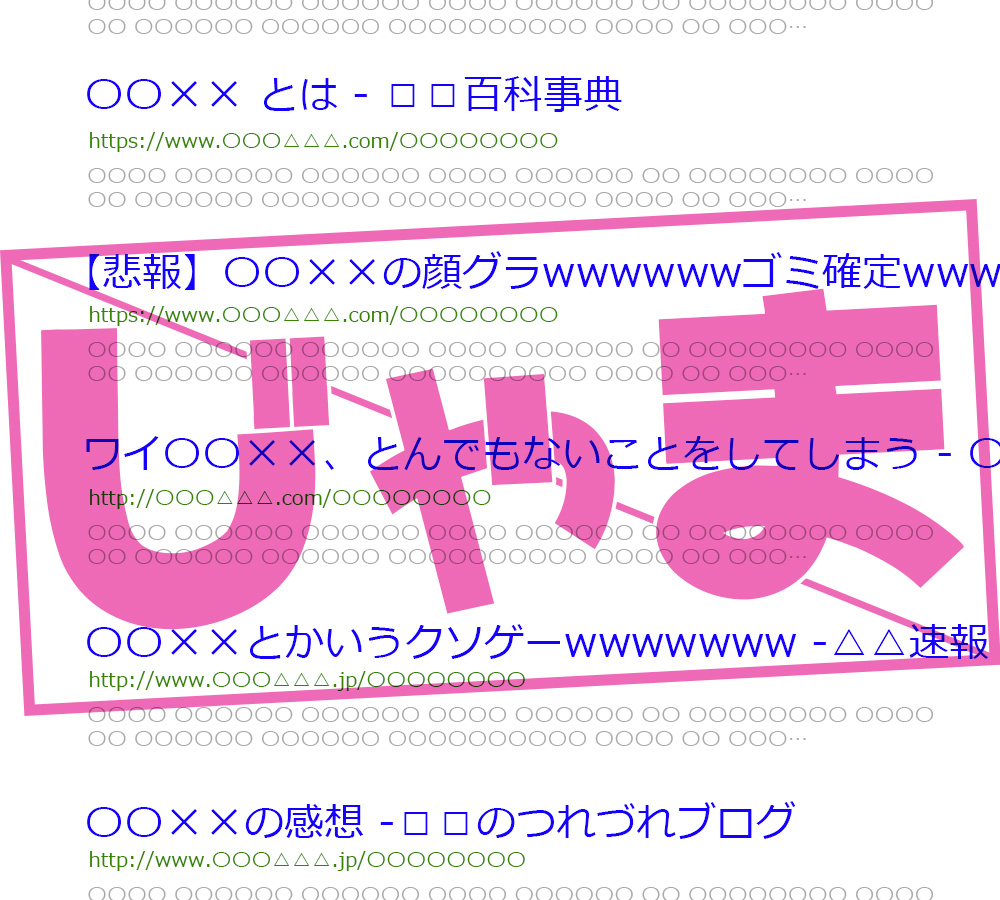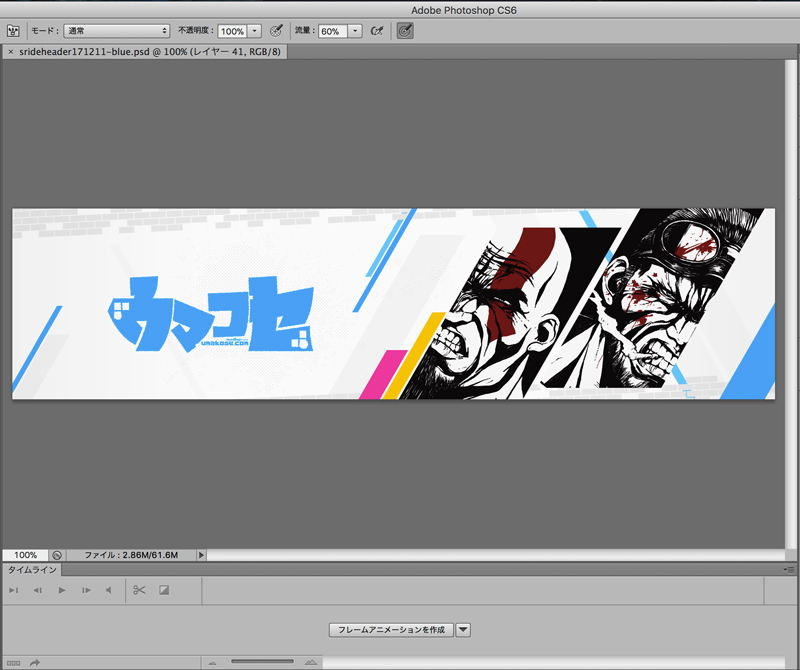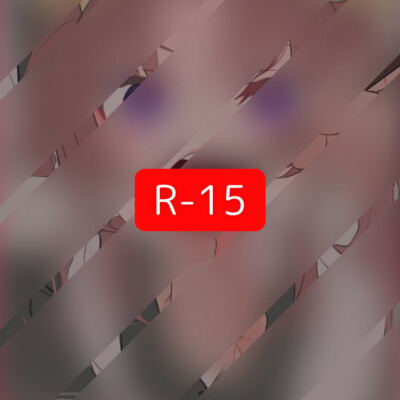ニュース系の感想や考察・解説を述べる記事を書くと必然的になるのが情報の引用(転載)元です。
これがオススメですという内容だと個人の好みや趣向が入ってしまうので、逆に引用は避けたほうがいいメディアを以下に並べました。
この記事を書いたのは、
- 【不適切な参考元】記事の情報源を見ると、一次情報のエビデンス(論拠)に乏しい。
- 【コメントの問題】コメントつき記事は荒れる傾向が強く、閲覧者側の気分を害する。
- 【説得力を下げる】内容がいいのに引用元のせいで説得力が下がってしまう。
「引用(転載)にはガイドラインを参考に、情報源明記」という基本ルールは守れても、質の悪い引用元で記事のレベルを下げてしまう、「もったいない」物書きが少なくないんですよね。
最悪のケースとして、信用性の低いメディアを引用した記事を書き、デマ拡散や風評被害・誹謗(ひぼう)中傷問題に加担してしまうなど、責任問題へと発展する可能性もありえます。
だからこそ、情報源は選定したほうがいいという趣旨です。

なお「絶対に引用してはいけない」というレベルでもない、内容による場合は『グレーゾーン』とします。ただし、問題や意見・反論を書くために引用する場合はこの限りではありません。
-
個人の見解です
ほかの意見もご参照ください
LITERA(リテラ)


内容がもうまとめサイト
一言で言えば、リテラは文章の質がひどく低い上に内容が不必要に長すぎます。
内容も反政権的かつ偏向(へんこう)的で、相反する対象(政権など)には徹底的に異端扱いにしますし、それだけなら左系メディアで済みますが、
- 「〇〇がブチギレ!」
- 「〇〇政権は主犯だ!」
などといった、とても物書きでご飯を食べているとは思えない内容で、煽(あお)るばかりの低品質なアフィリエイトブログかと誤解しそうです。
取材をほとんどしない
独自インタビューや取材コメントを取ることは少なく、会見や番組を観て感情的主張で長々と書く傾向があり、同じ内容でも、リテラだとその2~3倍の長さになる場合もままあります。
いわゆる『こたつライター』とよばれる人たちがほとんどで、ライターの質はお世辞にも高いとは言いがたいものです。

ビジネスジャーナル


無添加支持・陰謀論者は
好きかもしれない
リテラと同じく、株式会社サイゾーが配信しているメディア。
特に食品系の記事は一方的に煽るものが多く、添加物は危険、商品を名指しで保存料だらけで発がん性があるみたいな書きかたばかりで、その内容は商品・企業バッシングに近いです。
食品添加物に親族が殺されたのかと言わんばかり。

それゆえに、

「食品添加物・保存料は危険」と不安を煽る記事は問題。極端な意見に惑わされず、正しい知識を身につけるべきだ。
……という記事を掲載したときは、何かの冗談かと思いましたよ。
本人たちは「批判をしているだけ」と思っているでしょうけれど、本来の『批判』は言葉を選んで思いやる論理的な批評行為であるため、批判ができている人はほぼいません。
配信先だからか、ネットの意見はニコニコニュースのコメントから引用する傾向があります。
あれをネットの意見として扱うのは個人的に理解しがたい。

陰謀論・デマが多く、過去には捏造問題
上記のような過激なバッシングのほかにも、疑似科学を熱心に支持する経歴不明の執筆者が、その正当性を主張する記事を堂々と載せるなど、信ぴょう性にも疑問が残ります。
企業バッシングや陰謀論が多いのみならず、過去には、何度もデマ・捏造記事の掲載が明らかにされ、名指しされた企業から「事実無根だ」とプレスリリースを発表したこともありました。
「ビジネスジャーナル 捏造」と検索してみてください。

サイゾー系列は基本的に信用できる情報源ではない
一説ではアクセス稼ぎが目的のため、質より量で真偽のチェック体制が甘く、執筆経験がない初心者の記事でも掲載できるそうですね。
基本的に、サイゾー系列(サイゾーウーマン、日刊サイゾー、TOCANAなど)を読みものならまだしも、引用元としてふさわしくないし、参考にもすべきじゃないと断言します。
記事チェック体制はあくまでもうわさ話で、真実かは不明です。

キャリコネニュース


転職系アフィリエイトで
よく見かける
キャリコネそのものは株式会社グローバルウェイが提供する就職紹介サイトで、コンテンツのひとつであるキャリコネニュースは、特に職場に関するニュースやトラブルの記事を発信しています。
独自取材を元にした記事などもあるとはいえ、「ネットの意見」と称した記事は、情報源がニコニコニュース・ガールズちゃんねる・Yahoo!知恵袋・5ch掲示板など、引用元に疑問が残ります。
そのため、「キャリコネニュースは質の悪い記事が多い」と言われがちのようです。
なんで偏ったところから引用しようとするのだろう?

元サイトの印象がそもそも悪い
また、転職アフィリエイトブログでキャリコネのサービスが紹介され、キャリコネの企業採点システムが怪しいこともよく言われています。
たとえば、ホワイト度・ストレス度といった個人の主観で変わる内容をパロメーター項目で設定、評価の水増し問題などが指摘されていて、キャリコネ自体の心証が悪い人も少なくありません。
キャリコネ関係を調べると、「実体験口コミの質が高く素晴らしい」と言わんばかりにポジティブな意見だらけな記事が多く出るため、逆にそれが怪しく思われる部分もあるでしょうね。
転職という精神的にデリケートな時期もあいまって、なおさらそう感じる人もいるかもしれません。

とはいえホワイト度・ストレス度って変な日本語だよね。そんなのは上司や繁忙期次第でコロコロ変わるし、退職した人はそりゃ否定的に書くよ。

プレジデントオンライン【グレーゾーン】


ライターの質がまばら
プレジデント社が発信している、ビジネスマン向けのメディアサイトです。
個人的な見解では、エビデンスが明確な内容が多く、記事の執筆者も実績ある人が占めているため、当サイトやツイッターでも情報源・記事の感想として引用する場合があります。
なぜ引用のグレーゾーンにしているかといえば、「記事執筆者の中には、少し問題がある人も混じっている」ことが挙げられるからです。
あえてひとりを名指しするならば、『ウェブとバカは暇人のもの』の著者として知られる中川淳一郎氏ですね。
たとえば新型コロナウイルスによる飛行機マスク拒否騒動の記事も、主張が一方的で思慮に欠く内容だったため炎上状態になるものの、

マスク信仰の法律主義者さんとは話が合わない。屁理屈言ってるけど論理すり替えてるだけだし、あいつらバカだわ。
このように、「自分の書いた内容や論点に反省点はあったかもしれないから、次はそこを直してみよう」という発想・視点がなく、他責的で見下すような内容をブログで投稿していました。
相容れない相手だからって人格否定はよくないね。正しい批判の意識を感じない(=批判リテラシーが低い)。

自分が正しいは思考を退化させる
「自分は100%正しい、俺に意見する奴は敵」という考えかたは、人間的に成長せず、客観的思考を退化させます。
なぜ建設的な話し合いではなく、プロレスのように叩き・悪口合戦にするのかも理解しかねますし、その極端な考えかた、自分が正義思考は改めたほうがいいと思いますね。
中川氏のみならず、彼に攻撃的な応酬・バッシングをする人も同類です。

それゆえに「このメディアは引用してはダメ」ではなく、「記事を書いた執筆者は選んだほうがいい」になりますね。
まあこれは、どこのメディアサイトでも言えることだけど。

まいじつ


とにかく
悪口記事が多い
株式会社日本ジャーナル出版が運営するメディアサイトで、ここはとにかく悪口やバッシング記事が非常に多いです。
一部の否定派(アンチ)しか書き込んでいない内容を誇張して、
- 「炎上している」
- 「大バッシング」
- 「痛烈批判」
という見出しや記事を書くんですね。
そもそも「痛烈批判」って言葉として矛盾している。批判の意味を辞書で調べてほしいし、おかしいって気づかないのかな?

内容を見ても正しい批判をしている記事はなく、ニュース検索やアプリで上位に出てくるので、「まいじつは悪質なフェイクニュースサイト」と指摘されることもあります。
過去には「This story is produced(この物語は〜)」と文末にあったらしく、「虚構新聞と同じでフィクションでは?」と言われたそう。

「まいじつ」のニュースはすべて作り物らしい [ネットメディア]|今日のクソ記事
赤江珠緒、「まいじつ」のコタツ記事に怒る! [ラジオ]|コンテンツって言い方、嫌いだけど
引用ルールを守っていない
ルールも守られていないのも問題で、特にツイッターの内容を部分的に抜き出して改ざんしていることが、いくつも明らかになっています。
事実確認で自分も一次ツイートいくつか見て比較したけど、本当にやっていて言葉を失う。

ツイッターの引用ルールでは、内容を部分的に抜き取って印象操作をするといった意図的な改変は禁止されていますし、それは引用ではなく無断転載行為になります。
これを配信元が特にチェックもせず許しているんですから、コンプライアンス(企業モラル)としては目に余り、捨てアカウントを使ったツイートの自作自演疑惑まであります。
広告収入のためにわざと過激でネガティブな記事を書く印象が否めず、ネットのゴシップ系サイトは数多いといえど、ここは記事の質・モラルとともにかなり低いです。
知らない間にやってしまっている!?Twitterの無断転載に要注意!|Insta Lab
ニコニコニュース


独自記事はあるものの…
タイトルがお世辞にも品性がいいとは言いがたい内容が多いニコニコニュースの二次的な問題として、記事につけられたコメントツイートの内容が挙げられます。
あれはYahoo!ニュースのコメント欄といい勝負ですし、ネチケット・リテラシーが微塵(びじん)にも感じられない、現代のネット・SNSの負の部分が集結している感じですね。
その記事ツイートに不快感を抱かせることこの上なし。

Yahoo!ニュース


コメントの質がもっとも悪い
理由はニコニコニュースの項と同上。ずっと昔からコメント欄のネットマナーが悪い(いわゆるヤフコメ)と苦情を出している人が少なからずいるのに、今だに改善しませんからね。
追記
2019年あたりから、AIによるコメント選別や非表示をしています。ただし完全に消したわけではないので、引用不向きの評価に変更はありません。Yahoo!ニュースのコメント(ヤフコメ)の問題については、別記事でまとめています。
J-CASTニュース【グレーゾーン】


独自記事が多いため
悩みどころ
株式会社ジェイ・キャストが運用するニュースメディアサイトで、ここのコメント欄も非常に過激化しやすく、荒れやすい場所です。
コメントはリンクを押さないと見られないため、比較的良心的かもしれません。
これはJ-CASTニュースも過激な文言や煽るようなタイトル、報道の感想や炎上騒動をセンセーショナル(話題性)に取り上げる姿勢もおそらくは影響しています。
マスコットキャラクターも『カス丸』と自虐的ですし……

見定めが必要
ただ、すべてが煽り記事や質の悪い記事ではなく、エビデンスがあり冷静な視点で書かれたもの、独自アンケート調査、ここでしか扱っていない情報の記事もありますから、悩ましい部分ですね。
当サイトでもJ-CASTニュースの記事を引用することはあり、記事の選定には細心の注意と根拠を調べ、多用はしないように配慮しています。
iNSIDE(インサイド)


運営の姿勢が気になる
株式会社イードが運営するゲーム情報サイト。
10年ほど前までは任天堂のゲーム寄り、今は全ハードを扱うゲーム情報サイトです。掲載した記事が誤報や信憑性が乏しいと、訂正せずに無断削除をすることがあります。
掲載記事の削除自体はどのメディアでもあることなんですが、誤報の場合は訂正文をまず掲載するものですし、にも関わらず無断で削除する行為は、個人ブログと同じレベルです。
もうインサイドは見ていないから、今は改善されているのかは存じないけどね。

過去の話で、任天堂の宮本氏がかつて、ニンテンドー3DSのLL版は今後発売しないという旨の記事を出したことがあり、元記事には書かれておらず、記者の完全な憶測だったケースがありました。
その後無断で削除し、結局再掲載する意地の悪いことをしていたんですよね。これはコンプライアンス的にどうなんだと言われても仕方がないレベルだと思います。
Game*Spark(ゲームスパーク)


コメント欄がゲハブログ
同じく株式会社イードが運営するゲーム情報サイトで、インサイドとは姉妹サイトになります。
海外リーク情報や日本人向けの記事掲載をする内容が多い一方、ここのコメント欄もひどい内容ばかりで、いわゆるゲハブログ(ゲーム系のまとめブログ)のコメント欄そのもの。
煽りやネガティブバッシング(低評価叩き)、口喧嘩、ゲームハードの宗教化行為がまん延しており、純粋にゲームが好きな人からすれば、いい気分はしないでしょう。
コメント非表示にするボタンはあるものの、最初から非表示にすべきですね。
はてな匿名ダイアリー


言い逃げできてしまう
「保育園落ちた日本死ね」で話題になった匿名日記サービス。ひとつのブログを匿名の人たちが交換日記をしているような場所ですね。
正直ここは5chやYahoo!知恵袋、発言小町よりも問題が多く、特定の著名人や作品を中心とした誹謗中傷が多発し、意図的に過激に書いて話題性を仕立てる、いわゆる「釣り」の温床です。
基本的に投稿者情報は公開されず、返信も同一人物なのか非常にわかりにくいため、言い逃げも高確率で成立するので意見の説得力に欠けます。
というか、本気で相手してたらこっちの精神が病みそうな文章ばかりで精神衛生的に不健全。

週刊誌系メディア【グレーゾーン】


鵜呑みにしない人向け
たとえば日刊大衆や週刊アサ芸のようなメディアをさします。
週刊誌の記者が書いていますから、情報に正確さがなく、あくまでもうわさ話程度と判断したほうがよく、仮名で実名が書かれていない場合、創作話である可能性も考慮しないといけません。
「仮名・非公開だからでっちあげだ!」ではなく、「実名よりも情報源として確証が持てない」ということですね。
ゆえに話題の根拠(ソース)ではなく、あくまで「こんな話があるらしい」程度なら、引用してもいいとは思います。
その記事を真に受ける読者の質については別問題なので、「あくまでうわさ」と注釈を入れてあげるのが優しさ。

フリー百科事典【グレーゾーン】


素人執筆の危うさ
Wikipedia・ニコニコ大百科・ピクシブ百科事典などといった、ライターではない素人でも執筆できるサイトのことです。
特にニコニコ大百科やピクシブ百科事典は根拠がないのにも関わらず、独善的・主観的印象や感情的主張で記載したり、記事そのものを私物化する内容が非常に多い問題点があります。
ピクシブ百科事典はかなり深刻で、完全に無法地帯になっていますからね。
有料制で意見交換もされるニコニコ大百科のほうがまだ健全と感じるレベル(※実体験)

裏を返せば、
- 信頼できる情報源、書籍の記載
- 内容が客観的で中立・公平性が
こういった場合は可になるものの、たとえ信頼できる文章でも、将来的に別の匿名利用者によって信頼を失う文章へと改変されるリスクがあります。
引用するにしても歴史が長く、一定の秩序があるWikipediaに留めるのが無難です。
もちろんWikipediaにもデマや信ぴょう性に欠く場合があるから、便利だからって頻繁に引用するのは避けたほうがいい。

ツイッターなどのSNS【グレーゾーン】


拡散=確信ある情報
ではない
ツイッターをはじめとしたSNSも真偽不明な情報があふれていますし、
- 「有名人が発信・拡散しているから」
- 「いいね・リツイート数が多いから」
このような考えで安易に引用するのはリスクが高い行為です。
これらのツイートが正しい情報・事実・真実とは限りません。

都合よく使われる場合も
中には「こういった意見もあるよ」ではなく、ネット・SNS上の世論紹介と偏(かたよ)った情報ばかりを集め、誘導する目的で引用する人もいます。
いわゆる「印象操作」ですね。

話題ツイートからの記事作成ならわかるにしても、そのような煽動(せんどう)行為は、まとめコピペブログやトレンドブログのすることです(後述)。
自分も他者のツイートを引用することがありますので、その点は注意しています。
まとめブログ・トレンドブログ


誹謗中傷とデマの温床
まとめサイトやキュレーションサイト、いかがでしたかブログとも呼ばれているこれらのサイトを、引用元とするのもよろしくありません。
こういったブログの多くは収益目的で、記事の一部分を意図的に抜き出したり、話題性だけでよく調べずに掲載したり、コメントを印象操作して偏向的にする内容が多いですからね。
真偽は不明ながら、とあるテレビ番組でまとめコピペブログ管理者にインタビューをした特集で、

かつては収益のために悪魔に魂を売るような感じで、内容を精査せず、センセーショナルさを狙って記事を書いていた。
という旨の発言をされていました。たとえば西田敏行氏の薬物暴行デマを流し書類送検されたアフィリエイトブロガーも、同じような趣旨を言っていましたよね。
情報発信に対する責任感がない
ここでいうトレンドブログは、芸能・サブカルチャー・ニュース・政治系などですね。検索妨害されるのは、検索の手間や精神衛生上にもよろしくなく、大人の悪意そのものです。
これらのブログはデマと判明すると、謝罪もせず逃走を図るケースもあるため、引用元にすべきではありません。
極端な物言いにはなるものの、まとめサイト・トレンドブログは「考える力を奪い、自分の気持ちがいい情報しかないドラッグ」です。
日常的にまとめブログやトレンドブログを閲覧すること自体がオススメできない行為です。

危険性・詐欺などと警告する記事・サイト


要は「主語が大きい」サイト
たとえば『ネットの教科書』というサイトは、商品を名指しで危険だと不安を煽り、叩いた上で特定の商品を暗に勧めるなど、一部でステルスマーケティング(ステマ)疑惑が持たれています。
「危険性」「詐欺」といった刺激的な見出しを全面的に出す記事・サイトは警戒したほうがいい。

著名人の自己満足主張
その延長線上で、危険性や詐欺だと声高に警鐘を鳴らす人(著名人・専門家・学者・医者など)は、データを見せつつも「俺の自説は正しい」と正当性を押しつけたいだけの可能性が高いです。
当人たちのサイト・書籍の引用には注意を払ったほうがよく、「著名人だから正しいことを言っていると思わない」ことが大切です。
別に主張は全否定しないとはいえ、世の中には危険を煽ったり、極端な物言いで利益を得ようとする悪い大人がたくさんいます。
さまざまな視点から適切な情報選択をしましょう。

最後に:リテラシーを身につけることが大切


大切なのは、
「考えて疑うこと」
以上、引用にはあまりオススメしないメディアサイトなどをまとめました。
リストとしてまとめてはいるものの、この記事で一番言いたかったのは、
まず記事を書く前に引用元の質を精査すること。いい記事を書くならなおさら、しっかり正しく調べておくことが大切。

ここに話の本質があることを忘れないでください。
CHECK!
信頼性が乏しい引用元を利用すると、執筆記事のみならずサイトの信頼性にも揺らぎが生じてしまい、下手をすれば誹謗中傷や風評被害の共犯者になるリスクがある。また、質の低いサイトばかりを見ていると、自分の考えかたに偏りが生まれてしまったり、考える力を衰退させてしまいます。
- 自分を疑い、
- 情報をしっかり確認し、
- 真偽性を見極め、
- さまざまな情報を参照する。
リテラシーを高めるにはこれらがなによりも大切で、質のいい記事を書くならば、引用元にも気を配りたいところです。

寄付のお願い

ございます
-
当サイトはみなさまのご支援により、広告なしの実現やサイト維持をおこなっています。
記事や作品が気に入りましたら、支援サイトのご支援や寄付をよろしくお願いいたします。