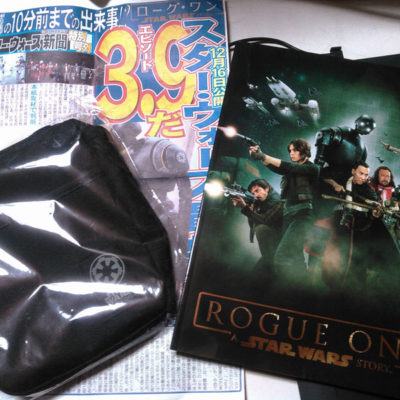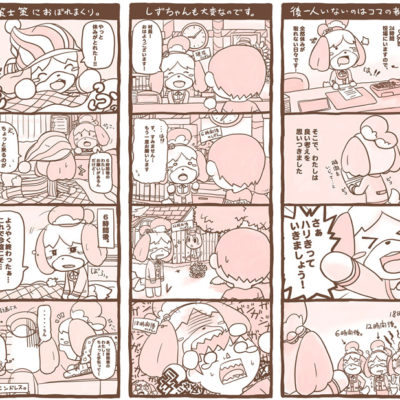ネット・SNSで情報発信をやっていると、一方的に反論を送りつけて無視したり、メールを削除したりアカウントをブロックして言い逃げされるケースを、一度は遭遇するかもしれません。
自分も幾度か経験していますが、正直彼らは「負け犬の遠ぼえ」だと自分で言っているのと変わらないと思います。
「負け犬の遠ぼえ」なんて刺激的だと思うかもだけど、ちゃんと意味があって使っているので最後に説明するね。

この記事では、
- 言い逃げの定義
- 言い逃げの心理
- そういった人への対策
ここを軸に述べていきます。
情報発信者の人ほど、うなずける・共感できる内容も多いかもしれませんし、言い逃げの経験がある人は、問題点を理解して改めることを心がけてください。
-
個人の見解です
ほかの意見もご参照ください
言い逃げの定義


「言い逃げ」とは?
『言い逃げ』の定義をネット辞書で調べると『言い逃(のが)れ』の同義語として出てきます。
言い逃れること。また、その言葉。言い抜け。言い逃げ。
言逃れ(イイノガレ)とは? 意味や使い方|コトバンク
ただこれだとネット・SNSで言われている意味合いと違いますから、
- 【言い逃げ】相手に一方的な主張を送りつけ、以降の意見・返信を無視・拒否。
- 【言い逃げ】主張を書いて連絡手段を一切見せないか、「〇日後に削除」と書く。
このような意味と定義し、当記事で主に扱うのは「1」の行為です。
「2」の行為も、情報発信者としては失格だけどね。

言い逃げの類語・例外
類語・別表現では、
- 『書き逃げ』
- 『言うだけ言って逃げる』
こちらになりますね。
なお、記事の感想をブログやSNSなどで書いて見解を述べたり、恋愛モノでよくある告白して逃げることは、今回の『言い逃げ』には該当しません。
言い逃げと検索すると告白関連が出てくるからね。

当記事の言い逃げとは繰り返すように、相手へ一方的な(特におとしめる・バッシング目的の)反論を書いて無視したり、削除・ブロックで拒絶する行為になります。
あとはX(ツイッター)などで@null返信をするのも、ある意味言い逃げ。フォロワー配慮と言うけどnullする内容を相手に送る自体がおかしい。

なぜ言い逃げをするのか


非生産的な行動をする
理由はなにか
一方的に送りつけて言い逃げするのはなぜか。もちろん彼らが自供しているわけではないものの、
- 相手を下げて優越感を得たい
- 意見できる人を演じたい
- 意見される覚悟がない
- 意見交換を勝ち負けだと思う
おそらくはこのような心理だと思いますので、以下から述べていきましょう。
相手を下げて優越感を得たい
いわゆるマウント(俺が上アピール)で、言い逃げする人の一番の理由だと思いますね。

個人的に気に入らないから、言い返してやりたい……!
相手をおとしめておきながら、だんまりを決め込んだり連絡手段を断つのは、正当性を主張するのに自分に自信がなく意見交換する気がそもそもないからとも言えます。
相手の評価を下げて自分の評価を上げようとするのを、『引き下げの心理』とよぶそうです。
こういう人の多くは自分自身の環境や意識に問題があるんですね。それから目をそらして他人に迷惑行為をして承認欲求を満たすのは、自分の首をしめているのと同じです。
心の中で勝ち誇っているんだろうけれど、それをしたところで身に置かれた環境の根本的な解決にならないだろうに。

他人にマウントをとる人のあまりに情けない心理|東洋経済オンライン
意見できる人を演じたい
中には、自分が当サイトに書いている論調や雰囲気をマネして送られてくる場合があり、肝心の中身が伴っていないパターンもありますね。
たとえば、

まるで〇〇だと言わんばかりに書かれていますが、その記述に対する客観的根拠は?
という文面が実際に送られてきたことがあります。
しかし、
- なぜ前提定義を無視したのか?
- 意図を読んだ上で言っているのか?
- 特定の文章に根拠を求める理由は?
- 根拠を提示するリスクは考えたか?
ここに対する見解・理由が述べられていないのみならず、全体的な文言も礼節に欠いているパターンが見られました。
用意した定義や意図を読み飛ばすし後半は内容が支離滅裂で、「なるほどね、特定の文面に反応しただけで語っているな」と思ったよ。

もちろん素直に根拠不足であるなら、真摯(しんし)に反省して改めるべきですが、本当に意見ができる人なら、これらをしっかりと把握した上で送ってくるものです。
あえて根拠を書かない理由
根拠を明記しないケースに言及すると、明記すると風評被害が発生しかねない場合、あえて根拠を載せないことがあるんですね。
その場合は記事で執筆全体の意図・前提定義を必ず説明しています。自分は記事執筆をタクティクス(戦略)だと思っているので、目的を設定し、計算をしながら執筆しています。
そこを無視して「根拠を出せ」と言うのは、記事を読まないで的はずれなことを言っている、ただの揚(あ)げ足とりであり、頭がいいアピールをする意識高い系でしかありません。
意見できない人ほど部分的に見て「根拠を出せ」って言いかたをするのが好きに思える。まあそれこそ根拠はないんだけどね。あくまでも経験論。

“意識高い系”が生まれてしまう心理学的なその理由|起業家.com
意見される覚悟がない
言い逃げする人には意見される覚悟がありません。
単純な理由で、意見される覚悟がある人は攻撃的な言葉を使ったり無視したり、連絡手段の消去やブロックなんてしませんからね。
当たり前といえば当たり前ですけどね。

それに意見される覚悟のある人は、人格否定や攻撃的な言葉にデメリットが多く非生産なのを知っているからね。

「相手を叩いて優越感を得たい」でも述べたのと同じで、自分に自信がないから(=意見に責任を持てないから)そのようなことをするんですね。
当サイトにコメント欄はありませんが、しっかりと連絡先を記載しています。
これは、
「意見するなら、意見されるようにもするのがスジ」だと考えているから。

ということであり、言い逃げを自らしない、情報発信をする人の責務ともいえます。
自分の考えに自信がないと、人の話を聞けなくなる|ハーバード・ビジネス・レビュー
意見交換を勝ち負けだと思う
意見することを勝ち負けだと思っていることも、理由として考えられます。
よくネット・SNS上では『レスバ(レスバトル)』という、意見することを口喧嘩やバトルのように扱うネットスラングをまま見かけます。
それどころか、
- 相手を論破する方法
- レスバに勝つ方法
このような方法論が一部で支持・求められている状態なんですね。
だから意見を送ることを対決のように思っているのかも。

そもそもレスバは、意見を戦わせて客観的に判断する討論とは別物で、ただ相手を全否定して論破し、優越感に浸るだけの行為です。
そこには何も生まれないし、それで勝ち誇っても何も残りません。討論をしているわけでもないので、知見が広がるわけでもないですからね。
レスバなんて心が貧しいか、問題解決能力が低いHow思考人間がする行為。そんなヒマがあるならスキルアップの勉強が有意義。

日本人は議論や討論、レビューが下手って言われる理由はここにあるのではないでしょうか。

意見交換の本質は「お互いに知見を深め合い、人間性を成長させること」です。
つまり意見を拒絶するとは、自分で人間性の成長を止めているのと同じです。
「論破したがる人」に共通する孤独感の正体|ダイヤモンド・オンライン
言い逃げは絶対悪か


「言い逃げ」って
悪いことなの?
ここまで「言い逃げ」に対するネガティブな部分を書いていますけれど、「言い逃げ」そのものは絶対悪ではありません。
あくまでも「相手をおとしめる目的で意見を送りつけて、そこからの返信を拒否する行為」が問題なワケだからね。

定義の項目で述べたように、記事を引用して自分のサイトやSNSに見解を書くのは言い逃げではありません。
ただし、本人に説明を求められて無視するのは『言い逃げ』です。

また、明らかに話がつうじない人、日本語が意味不明・支離滅裂な人に対し、「今後意見を送るつもりはありません」と前置きした上で、コメントをして拒否をするのは自分への自衛策です。
こういった人は答えありきで聞く耳を持たず、話が平行線なので話し合いが不可能です。
「話せば理解してもらえる」とやりとりを求めると、粘着されたり事実無根な内容で悪評を広められるなど、時間を無駄に浪費されてしまい、本当に精神を病みます。
しかしだからといって、相手をおとしめる目的で、礼節に欠いた攻撃的な文言や強い言葉を使うのはダメです。
それこそ記事で述べている一方的に言い逃げする人と同じですし、ちゃんと前置きして「叩く」のではなく「アドバイス」として、言葉を選び優しく伝えることを忘れてはいけません。
話がつうじない人に意見するのはリスクが大きすぎるから、関わること自体オススメしない。

ここがあるかどうかが大きな違い
わかりやすく区別・明確化をするのなら、
- ちゃんと内容を熟読したか
- 意図を把握しているか
- 意見される覚悟があるのか
- 礼儀をわきまえているか
要はここの全部を理解しての行動なら、言い逃げそのものは悪ではありません。
話がつうじない相手は関わること自体をオススメしませんが、ちゃんと礼儀として今後送らない旨の断り書きを入れ、正しく意見を述べてください。
ひとつでも欠けていたら、問題のある言い逃げだよ。

言い逃げする人への対策


対策は必要だよ
言い逃げする人の対策で自分がしているのは、
- 注意事項に「言い逃げお断り」と書く
- コピペできないようにする
- 記事改善として利用する
上記の点になるので以下から述べていきます。
「言い逃げお断り」と書く
自分を守るためにも、お問い合わせページなどに「言い逃げお断り」は書いておきましょう。
絶対的な抑止力にはならないにしても意思表明にはなり、言い逃げされた場合の対策も明記することで、「言い逃げにはなんのメリットもないよ」と宣言することができます。
当サイトでは言い逃げがあった場合、その主張は参考にすることはあっても、指摘があった旨は一切記載しないと明記しています。

コピペできないようにする
もしサイトを改造できる人であれば、以下のタグをサイト全体、もしくは記事全体の枠組みを構成するCSS(SASS)に入れてください。
user-select: none;これでコピペができなくなります。
コピペ不可だと、記事を引用して意見する方からすれば非常に不便なので、ケースバイケースです。

自分宛に来る言い逃げは、記事の内容をコピペしてマウントをとろうとするケースが多いため、当サイトでは意図的にコピペ不可の施策をしています。
記事改善として利用する
自分宛に来た内容はおおかた、部分的に抜き取って重箱のすみをつつく反論や、明記した事前定義・意図・執筆目的を読み飛ばされるケースが多く、
ちゃんと定義・意図・目的を書いてあるじゃない。『木を見て森を見ず』って言葉を知らないのかな……

このようにあきれてしまう部分はあるにしても、そのような内容が来たということは、記事をもっと改善できるということでもあります。
意図などをちゃんと明記しておらず、それで異なる解釈をされた場合は記事の書きかたが悪いので、反省したほうがいいです。

言い逃げは言ってしまえば権利・文章の著作権放棄であるため、上述のとおり「記事の指摘を受けました」と書く必要はないと考えています。
CHECK!
利用するものは利用して、より説得力のある記事へと改善させる。そう考えると、言い逃げは情報発信者へ構成改善のアドバイスを無料提供しているんですね。
また、言い逃げした人の意見の問題点を徹底的に指摘・言及した内容を載せることで、言い逃げのリスクと抑止、自分に意見するとはどういうことかを、閲覧者にわからせるようにしています。
彼らには「ちゃんと文章読んでないでしょ」と思いつつ、「ほら、これで言い逃れできないぞ?」と、読み飛ばしの言い訳をさせないようにしよう。

最後に:一方的な言い逃げは成長できない人がすること


自分で負け犬の遠ぼえを
やっている
ここまで、言い逃げという行為について述べていきました。
CHECK!
言い逃げは必ずしも絶対悪ではない。しかし話し合いができる相手に一方的な主張(特に相手をおとしめる目的)を送って無視をする言い逃げは卑怯そのもの。こういった一方的な言い逃げ行為は、
- 「意見に自信が持てません」
- 「問題の本質を見られません」
- 「ビビっているチキンです」
- 「文章を読むことができません」
そう敗北宣言・負け犬の遠ぼえをしているのと同じで、そもそも意見交換を勝ち負けだと思っている自体がおかしいことに気づいてほしいものですね。
チキンで犬とは……?

意見交換の本質は「負かし合い」ではなく「双方の成長」です。意見を拒否するとは、いつまでも人として成長できないということでもあります。
「負け犬の遠ぼえ」とタイトルに書いているのは、そのぐらい自分を価値を下げる行為であるという意味だからだよ。

言い逃げする人には軸がない
自分宛に来る、叩きたい目的で言い逃げする内容は、情報発信者なので目をとおしているものの、
- 何が言いたいのかわからない
- 言葉選びがマウントとり
- 文章構成が支離滅裂
- 記事の内容を無視している
本当にこのような内容ばかりで、真面目に返信を考えるのも悩んでしまうほどです。
まあ言葉を選んで返信を書いたところで返せないんだけど、だから言い逃げするんだろうなって思う。自分が反論に言及したら言い返せないと認めているから。

中には自分が当サイトで書いているような記述方法や論調をマネて送ってくる人もいます。
しかし上記で述べたように、内容が伴っていない場合がほとんどですね。
言葉悪くてゴメンだけど、他人の書きかたをマネないと反論できないって恥ずかしくないの? 意識高い系じゃなくて「意識高い」にしなきゃダメでしょ?

あえて少々煽(あお)る書きかたを意図的にしていますが、この言葉の意味をしっかり理解していただかないといけません。
自分の意見に自信がないのなら言えるように訓練したり、本で勉強をして自己研鑽(けんさん)するものです。
それをしないから他人のマネごとしかできないし、中身が伴っていない意識高い系なんですよ。
意見の質向上のほとんどは経験とテクニックであり、少なくとも自分を含め、本当に意識が高い人、意見が言える人は常日頃やっています。
ちなみに自分の意見レベルは「社会人として最低限のレベル」だよ。本当に意見できる人はいつ見ても勉強になる。

意見するなら意見される覚悟は持つべきで、やむをえず自衛のために言い逃げするのなら、ちゃんと相手に礼儀を払い、言葉を選んだ「アドバイス」として優しく伝えるべきです。
これはネット・SNSだろうが実社会だろうが関係ありません。それがコミュニケーションであり、人としての礼儀です。

寄付のお願い

ございます
-
当サイトはみなさまのご支援により、広告なしの実現やサイト維持をおこなっています。
記事や作品が気に入りましたら、支援サイトのご支援や寄付をよろしくお願いいたします。