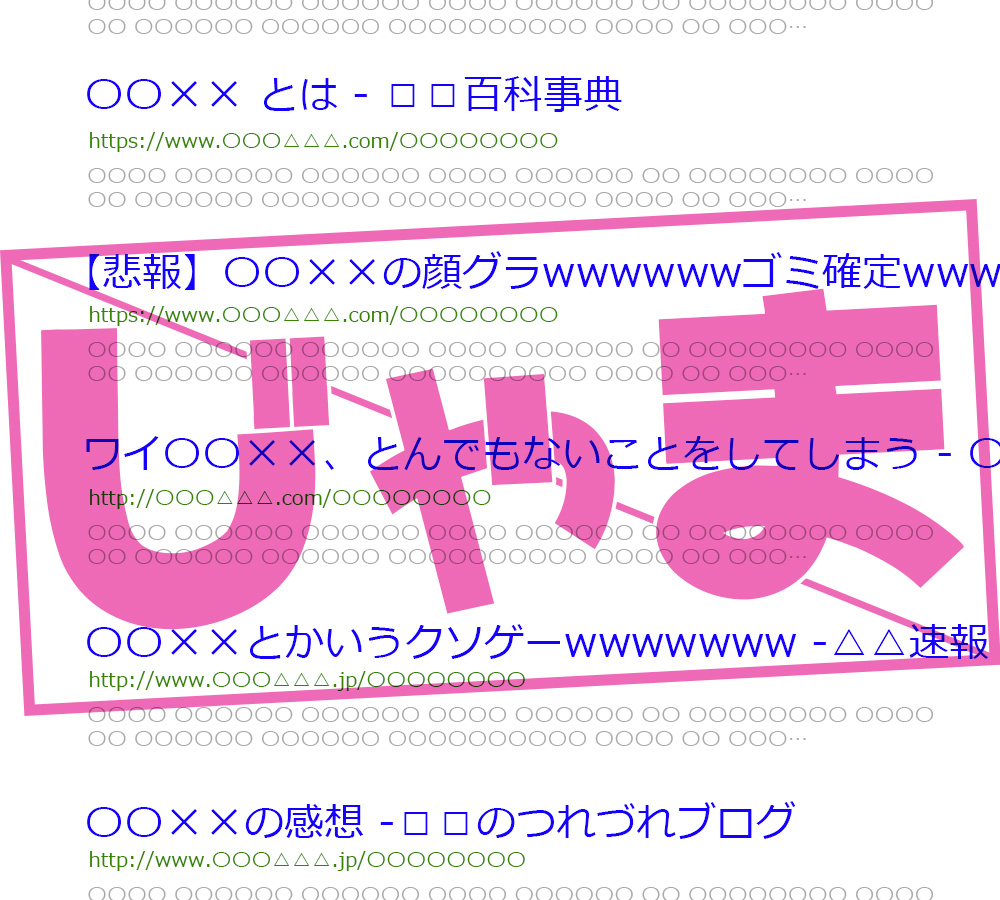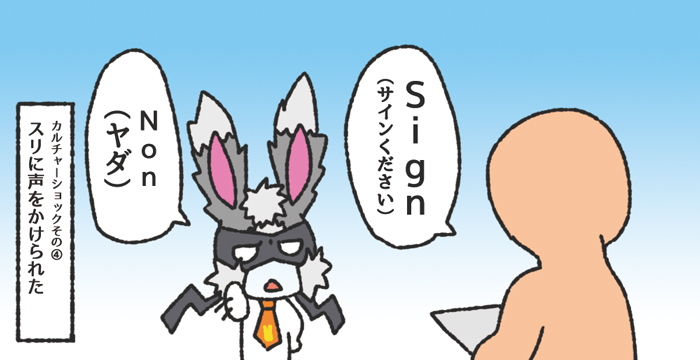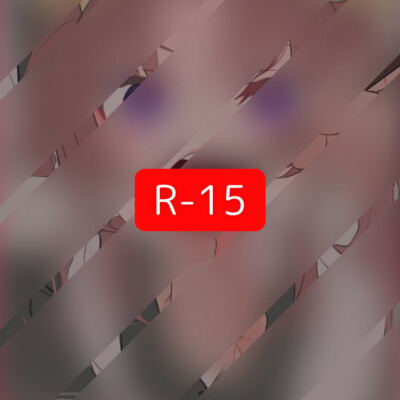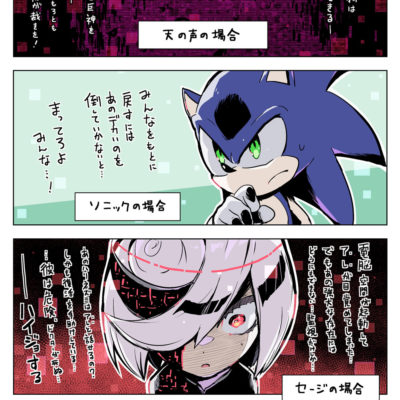例の東京五輪エンブレムのパクリ問題で見られた、アーティストを気取るデザイナーの姿勢や、すぐパクリと呼ぶネット・SNSの風潮に違和感を感じますので、その見解を述べていきます。
-
個人の見解です
ほかの意見もご参照ください
東京五輪エンブレムのパクリ問題について


デザイナーとしての
姿勢に疑問
まずエンブレム問題。自分の意見をまとめると、
- 「あのシンプルな造形をパクリは言いがかり。しかし佐野氏の弁解には違和感」
- 「ネット・SNSで見られた、擁護(ようご)派のデザインに対する意識の形骸化」
このようになりますね。
デザイナーはパクリが普通
語弊のある言いかたにはなりますが、デザインの世界(ロゴ・シンボル・レイアウトのデザインなど)でパクリは普通です。
ただしこれは、「コピーやトレースをして盗用・横取りする」という意味ではなく、
CHECK!
世の中のデザインは既存物の組み合わせで作られていて、クリエイターたちは既出のテーマやパーツ、流行を組み合わせて、新たな価値をつくり上げるのが仕事。という部分は留意いただければと思います。
デザインの本質は「指標・広告」。独創性は二の次で、アーティスト気取りのデザイナーも、すぐパクリという人も、ここを理解していない場合が多い。

デザインの9割は理論と流行
デザインには法則(デザイン理論)があり、
- 違和感がない配色(ドミナント配色など)
- 安心できる大きさ・配置(貴金属比など)
こういったものがあります。
これは伝統のほか、人間工学や心理学のレベルで科学的に決まっていて、その中で、しかも記号の組み合わせのようなデザインをするわけですし、時代背景や流行(トレンド)も影響します。
確立されたデザイン理論と流行がある中で、完全独自かつ大衆に迎合されるデザインができる人は、0.1%未満の超天才だけだよ。

ゆえに「幾何(きか)形態の組み合わせのため、意図せず偶然に似てしまった」ではなく、

類似性はあるが、デザインに対する表現や考えかたが違うので似ていない。
そう主張したことには違和感がありましたね。
ましてや一度もパクリをしたことがないって、デザイナーだったらまず出てこない言葉です。
アーティスト気取りのデザイナー
そして佐野氏のみならず、ネット・SNSのプロデザイナーの一部に見られたのが、ロゴ・シンボルデザインをアート作品に見立てていたことです。
自分もデザインを作る身なので言わせていただくと、ロゴ・シンボルデザインにアートの考えかたを持っていくのは、大きな勘違いです。
CHECK!
ロゴ・シンボル・レイアウトなどデザインは、依頼者が考える意図を反映するのも大切だが、世間一般の人たちに、何をさしているのかをわかりやすく理解してもらうための指標であり、広告。コンセプトを制作者が説明するのならまだしも、赤の他人デザイナーが、
- 「このロゴはこの作家の意匠を〜」
- 「この色合いは〇〇時代で〜」
とか言い出すって、デザインの本質をはき違えていて本末顛倒(てんとう)であり、
アーティストでもしたいのなら、デザインではなくアートの世界でやってくれません?

……ってなりますね。
デザイナーは相手の意向よりも自己満足を優先したり、独りよがりで仕事する人が少なくないですけど、上記の人たちはそのタイプかもしれません。
仕事でもアーティストのように振舞うデザイナーに会ったことがあるね。なんで顧客を無視して自分ばかりを優先するんだろうか?

ネット・SNSの「なんでもすぐパクリと言う人」問題


なんでもかんでも
パクリと呼ぶ風潮
この問題でパクリという言葉がいろいろ使われましたが、ネット・SNSにおけるパクリの使いかたについて疑問を抱くので、ついでにそちらも挙げていきましょう。
特にアニメやゲーム・映画のサブカルチャー関連では多いからね。ひとつ覚えのようにすぐパクリパクリって言いたがる人。

似ていればすぐパクリと呼ぶ

この作品は〇〇と似ていますが、〇〇のパクリですか?
「似ていますが」までならわかりますけど、二言目に「パクリ」が出るのは首をかしげます。
経験上、このようにすぐパクリと言い出す人は、あまり物事を深く考えていないし、視野が狭く本質を見る意識がない人だろうと考察します。
キツい言いかただけど、見識の狭い人が思考停止の思いつきで言っているということ。

だから既視感があるとすぐパクリ扱いですし、本人に悪気はなくても、言われた側からしたらいい気分はしませんよね。

先に伝えたとおり、完全な無から有をつくるのは、デザイン・アート理論が発達し、さまざまな創作物があふれる今の時代では困難です。
既存のものを組み合わせて新たなアプローチをするもので、先人たちが積み上げたデザインの人体工学・心理学・トレンドは「解」であり、パブリック(共有財産)です。
「トレース疑惑」で盛り上がるのも同じ。明らかに悪質なものは対処が必要だけど、構図が似ているだけとか、単にあら捜しで叩いているさまは異常。

こういう人たちは「パクリ」と叩いて万能感や自己肯定感を満たすなど、その行動の本質は別のところにあるかもしれません。

その理屈でいうと…
もし、彼らのパクリ理論で極端に言うならば、昨今のストーリーマンガは手塚治虫のパクリです。
女の子などの可愛いキャラクターのほっぺに「///」を入れるのも、コマ割りに大小のリズム感を作るのも、「シーン」の効果音(オノマトペ)も、すべて手塚治虫の発明とされています。
マンガの神様は文字どおり、「現代マンガをつくった神」ですね。なお表情の記号は「漫符」といい、「///」の起源は諸説あります。

ストーリーマンガを見て、

コマ割りが似ているけど手塚治虫のパクリですか?
そんなことを言う人はほぼいないですからね。
エヴァは旧約聖書のパクリ、なろう系はゼロの使い魔のパクリ、異世界転移はナルニア国物語のパクリ……少し考えれば収拾つかないのわかるよね。

建築や家具・絵画や機器にいたるまで、世の中のものはパクリから発展しています。著作権やパブリックドメインなども深く理解していないように思えます。

無音を表す「シーン…」は手塚治虫が生み出した? マンガ界の「大発明」を振り返る|マグミクス
ストーリー漫画|Wikipedia
著作権は永遠に保護されるの?|公益社団法人著作権情報センター CRIC
流されるままパクリと呼ぶ

これって〇〇のパクリでしょ? ネットにも書かれてるじゃん。
自分の考えを持たない・考えないので、周りの意見や主張に流されるか、ノリでパクリだと言っている状態ですね。
まとめサイトやSNS、掲示板コメントでも見られる光景です。

佐野氏の件は東京五輪という一大イベントなだけに注目度が高くなっただけであって、世の中のデザインは似ているものであふれかえっています。
繰り返すように、すべてパクリと言えば収拾がつかないし、デザインの本質を理解していません。確かにロゴは対象のシンボルではありますが、主役ではありません。
流されて言うのは意見じゃない。「意見をした気になっている」だけの意識高い系だよ。

知ったものと似ていればパクリ

これって俺の知っている〇〇のパクリだよね。
こちらは元ネタを知らないがゆえに勘違いしているケースで、元となった作品などをパクリという人って、たまに見かけますよね。
一例を挙げると、ニンテンドーDSで発売された音楽ゲーム『押忍!闘え!応援団』シリーズを、無料音楽ゲームの『Osu!』のパクリと(ネタか本気か)勘違いする人が少なからずいます。
時代が時代だから、osu!の元ネタを知らない人が増えているのが悲しい。応援団シリーズは名作だし、わかりやすいマンガ・キャラの描きかたの理想的なお手本。

しかし、応援団シリーズの海外ファンがまねて作ったゲームがOsu!ですから、あえて言うならOsu!が応援団シリーズのパクリなんですね。
初代応援団は2005年7月28日発売、osu!は2007年9月16日に配信されています。
上記の例からもわかるように、自分が先に知ったものがオリジナル、それ以外はパクリは暴論であり、支離滅裂であるのがわかると思います。
それは「無知」ではなく「無恥」だよ。思考の停止が招く愚行の最たる例じゃなかろうか。

応援団(曖昧さ回避)|osu!
『押忍!闘え!応援団』開発者、シリーズ復活に意欲を見せる。「うまくいけば次のプラットフォームで」とも|AUTOMATON
パロディ・オマージュ・リスペクトもパクリ

パロディとかもっともらしく言ってるけど、要はパクリじゃん。
- 「製作者がパロディだとしても、見る側には関係ない」
- 「パロディでも元ネタの作者がパクリと感じればパクリ」
こちらは上記の例とは異なり、需要と供給の関係、受けとりかたを考えさせられます。
後者に至っては、Wiiで唯一のZ指定(18歳以上)ゲーム『MAD WORLD』で、主人公のジャックが筋肉バスター的な技を使い、作者のゆでたまご氏が激怒したケースもありました。
この話題に関しては答えを出すのは難しいですね。
このあたりは自分も悩みどころ。ただどちらにせよ、元ネタにしっかりとリスペクト(敬意)を持つことは忘れちゃいけないね。

ゆでたまご嶋田先生、ゲーム内でのキン肉バスター・パクリに「作品作る気うせるよな!!」~モハメドヨネは公認|ブラックアイ2
わざとパクリと言っている

【悲報wwwww】〇〇、△△パクリだったwwwww
最後に考えられるのは、わざとパクリと言っている状態ですね。これは物書きや動画投稿者がブログの見出し、動画のサムネイル画像で、
- 〇〇のパクリゲーwwwww
- 〇〇のパクリ確定!
- 〇〇のパクリ疑惑が浮上して草
と、教養のなさや品性に欠くような文言を並べて煽(あお)る行為です。
なぜこのようなことをするかといえば、大抵はアクセス数稼ぎ・広告収入目当てなんですね。
アクセス・金目的のために煽るんですから、正直レベルの低いことをしているなと思います。「パクリ?」と書いておいて、中身でパクリを否定して魅力を語る人もいますが、少数派です。
中には閲覧数・金目的ではなく、性根ひん曲がった真性の人もいるけどね。ガチでヤバい人だから関わらないでおこう。

最後に:デザイナーの姿勢も、パクリ呼ばわりする風潮も問題


ものづくりからすれば
どちらも迷惑
デザイナーの世界、特にロゴやシンボル、レイアウトなどの世界では、既存物をパクって新たな価値を見い出すことは普通です。
ただしこのパクリは「トレースや模倣で盗用、権利や影響を横取りする」ということではなく、
CHECK!
先人たちが積み上げてきた理論・人間工学・心理学・流行を取り入れる。という意味であり、パブリックなんですね。
デザインの本質は「見る側に目的を伝えること」であり、世の中のデザインは「大衆に受け入れられた正解例」なんですよ。
アーティスト気取りをするデザイナーはそもそも、ここを理解していないんですね。
パクリ自体は悪いことではありません。良いパクリと悪いパクリを区別化する必要があります。

なんでもかんでもパクリ呼ばわりする問題
また、すぐパクリパクリと呼ぶ風潮に疑念を抱かない人も、思慮として浅く、かなりの問題です。
問題に「著作権がー」と言う人は大体、著作権の本質をわかっていない。創作的表現・パブリックドメイン・二次利用・親告罪の定義・目的を説明できないと思うね。

開口一番パクリ、便乗してパクリ、後から知ったものをパクリと呼ぶのって、これを思慮深い意見だとは思えないですね。
本人たちは深く考えておらず、

え? ただのノリでしょ?
と思っているでしょうが、こういった人たちって周りに流されるだけで自分の意見を持たないパターンが多く、言われる側、好きな人からは気分を悪くするだけですからね。
相手の気分を不当に害して「ノリでしょ?」と言い訳するのは無責任であり、知見不足でパクリと言っているのなら、その無恥な態度を改めていただきたいものです。
またブログの見出しや動画のサムネイルでパクリだと煽っている人は、大抵アクセス数稼ぎか広告収入目当てです。見かけても関わらないようにするか、悪質なら通報でもしましょう。
すぐパクリ呼ばわりは思考停止と同じ。理由も思いつき、虎の威を借りる、周りが言っている……そんなに自分がないのかと。

まだパロディとパクリの境界線を語るほうが建設的です。

パクリ論争は起源論争ぐらい不毛。語るならHowじゃなくWhyの考えをしてもらいたいし、意識高い系でしかない。

デザイナー側も言う側も、その点は反省して考えるようにしてほしいですね。

寄付のお願い

ございます
-
当サイトはみなさまのご支援により、広告なしの実現やサイト維持をおこなっています。
記事や作品が気に入りましたら、支援サイトのご支援や寄付をよろしくお願いいたします。